 Plant hack‗JP
Plant hack‗JP 連日の猛暑に立ち向かう——エタノール散布で農作物の熱ストレスを和らげる科学的手法の最新研究まとめ
連日の猛暑で農作物や家庭菜園がダメージを受ける中、低濃度エタノール散布による耐熱性強化が注目されています。トマトなどで実証された最新研究と実践方法を解説。
 Plant hack‗JP
Plant hack‗JP  植物共暮
植物共暮  研究
研究 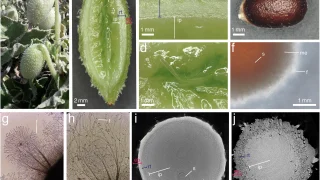 研究
研究 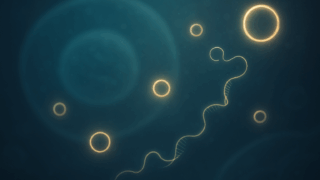 研究
研究 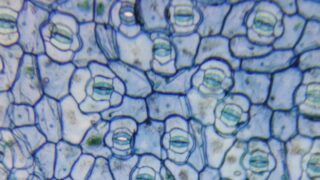 研究
研究 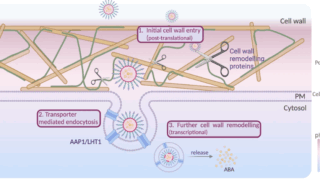 研究
研究  研究
研究 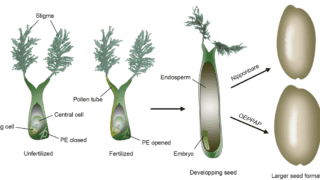 研究
研究  研究
研究